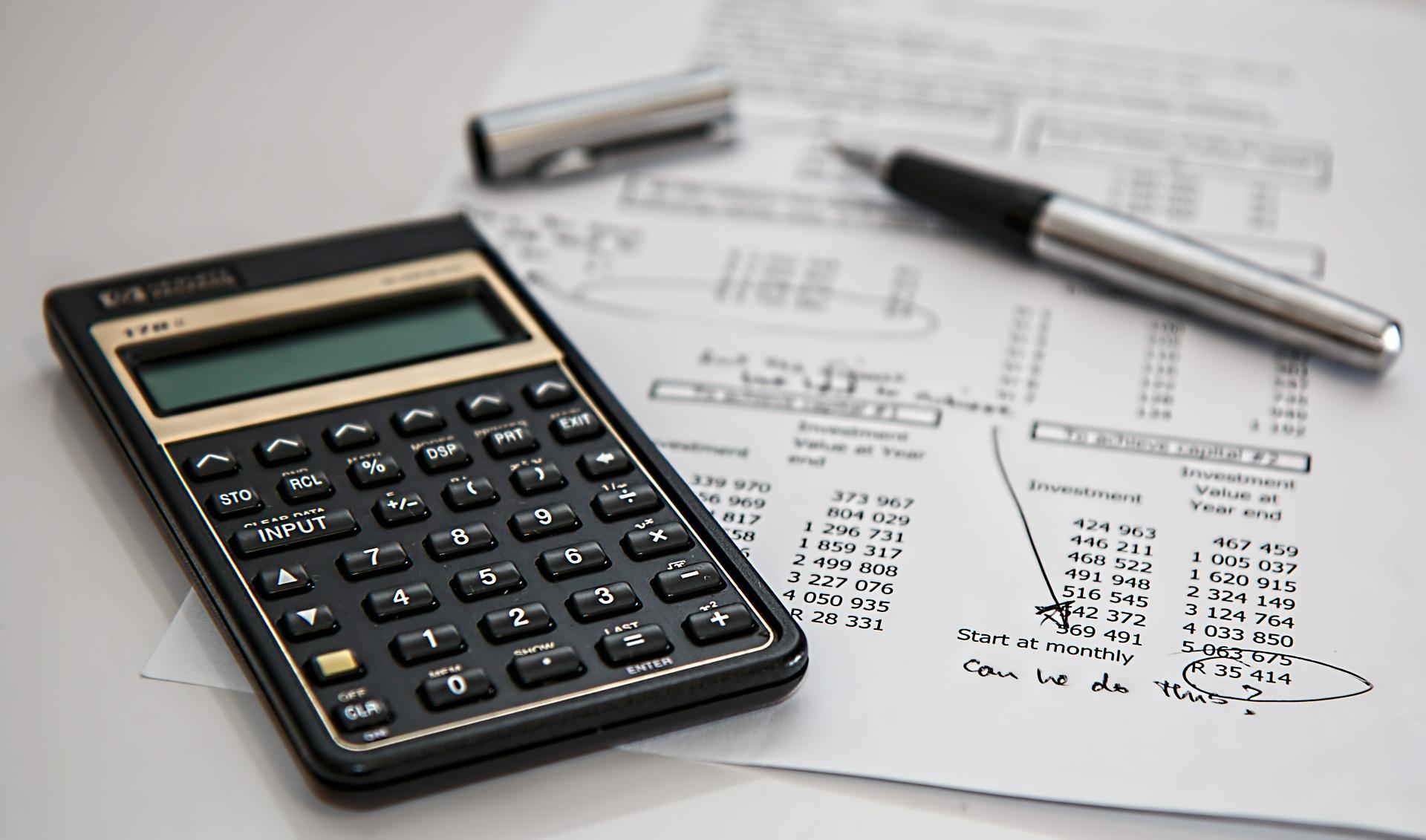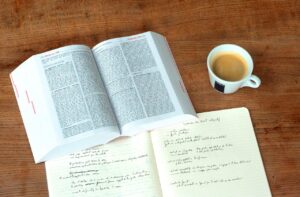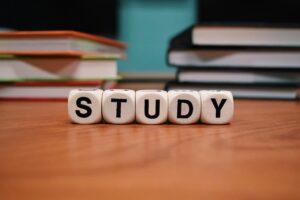試験時間がたっぷりあって時間に余裕がある中で解答できるならあまり意識する必要はないかもしれません。
しかし、今の税理士試験は120分という制限時間では到底解ききれない量の問題が出題されるのが当たり前のようになっています。
そこで試験対策で重要になってくるのが問題の取捨選択。
取捨選択をするケースとしては、理論問題より計算問題が中心になってくるかと思います。
限られた時間で自分の解答用紙を合格答案にするためには、問題の取捨選択は必至です。
訓練しないと適切な取捨選択ができない
問題の取捨選択は「解答する」と「解答しない」に分けるというより、優先順位付けに近いです。
「先にこの問題を解く」
「この問題は後回し」
税理士試験の特徴の一つとして競争試験が挙げられます。
周りの受験生が得点する箇所は確実に得点して落とすわけにはいきません。
その得点する箇所は基礎的な論点や比較的簡単に解答できる問題が中心となります。
その部分を確実に得点に結びつけるためには、基礎論点であろうと思われる問題を的確に読み取って「先に解く」に分類する必要があります。
一方で難しい論点で他の受験生も後回しにするような論点は「後回し」に分類しておきます。
一見すると他の受験生と差をつけるために、後回しにするようなところも「得点しなければ」と思われるかもしれません。
しかし無理に解こうとしてしまうと、かえって時間をロスしてしまいます。
そうなってしまうと周りの受験生が得点できている問題が手がつけられなくなる場合があります。
これが影響して本来取らなければならない問題が解答できなくなると、合否に大きな悪影響を及ぼしてしまいます。
「後回し」の問題は「先に解く」問題を全て解き終わってから着手することになるので、時間によっては解ききれないことになってしまう可能性もあります。
しかし他の受験生も同じように解けていないのなら、それでも問題ないのです。
一番やってしまうとマズイことが、
- 他の受験生が解かないような難しい問題に着手してしまう。
- 結局中途半端な解答になってしまい、時間だけ使ってしまう。
- 他の受験生が解答できているところに焦って着手する。
- 焦りからケアレスミスをしてしまうor時間不足で解ききれない。
この状態に陥ってしまうと、なかなか合格点を確保するのが難しくなってしまいます。
そうならないように迅速かつ適切に問題の取捨選択をする必要があるのですが、これはすぐにできるものでもありません。
日頃の問題演習の時から取捨選択の練習をしておかなければなりません。
取捨選択は問題を解き始める前にしておく
問題を解く前は全体像を把握するため、問題の最初から最後まで一読(素読み)をすると思います。
この段階で可能な限り取捨選択はしておいた方が良いと思っています。
もちろん最初の素読みの段階なので、細かく問題を見て判断するまでの時間はありません。
あくまでパッと見た印象で判断します。
この辺りは日頃からの問題演習で解いてきた経験がものを言うところになってきますが、
いつも解いているような問題文で「解ける!」と判断したものは「先に解く」
パッと見いつもと違うような、よくわからない問題や長文で「?」となってしまったら「後回し」
普段の勉強から取捨選択を意識して解くことで「この問題が出たらすぐ解けるな」とか「この問題は解けるけれど時間がかかるな」というのが少しずつわかってきます。
日頃の勉強は問題に解答するための解法を学習することが中心だと思いますが、取捨選択の判断の訓練もあわせてすることにより、次第に取捨選択を素早く的確にできるようになってきます。
最初に判断しきれない問題もある
実際問題を解いていると、先に解くと判断した問題も実際に着手して解いてみると解けないということもあります。
「一度手をつけた問題はもったいないから最後まで解き切りたい」
私も最初はこのようなタイプでした。簿記論でよくやってしまってました。
深追いすればするほど逃げられなくなって時間を費やしてしまう。採点すると結局間違えていた。
練習も含めて何度も経験しました。
解き始めて「これは今解くべきでない」と感じたら、勇気をもって思い切ってその問題を飛ばす(後回しにする)ようにしてしまいましょう。
確かに途中で止めてしまうとそれまでの時間はロスしたことになりますが、まだリカバリー可能な状態です。
他の問題でしっかり点を確保できれば大丈夫です。
他の問題が一通り終わって時間があれば、戻ってこれば良いのです。
無理に深追いしすぎて取り返しがつかないような状況にならないように、着手してから「後回し」に切り替えるのも場合によっては必要です。
周りに負けないような答案を作る意識を持つ
競争試験となると「他の受験生が取れないようなところも正答しなきゃ」という意識がどうしても出てきます。
その意識のまま問題を解こうとすると、難題にも着手してしまいます。
まずは「他の受験生に負けない答案を作る」ように心がけることが大切だと思っています。
簡単な問題や基本論点を中心に、周りの受験生が得点できるところを自分もしっかり得点しに行く。
一見これだけでは「当たり前のこと」で他の受験生と差がつかないと感じると思います。
しかしその「当たり前のこと」を確実にものにするのが難しいところ。
これは自分もそうだし、他の受験生も同じです。
その「当たり前のこと」を自分がしっかりこなすだけでも、周りと差がついて意外と上位に位置していた、
なんてことも十分にあります。
まずはその当たり前の部分が問題のどこなのか、どれを優先的に解けば良いのかを迅速かつ的確に判断できるようになるためにも、問題の取捨選択を日頃から訓練しておかなくてはいけません。
それでは、また次回。