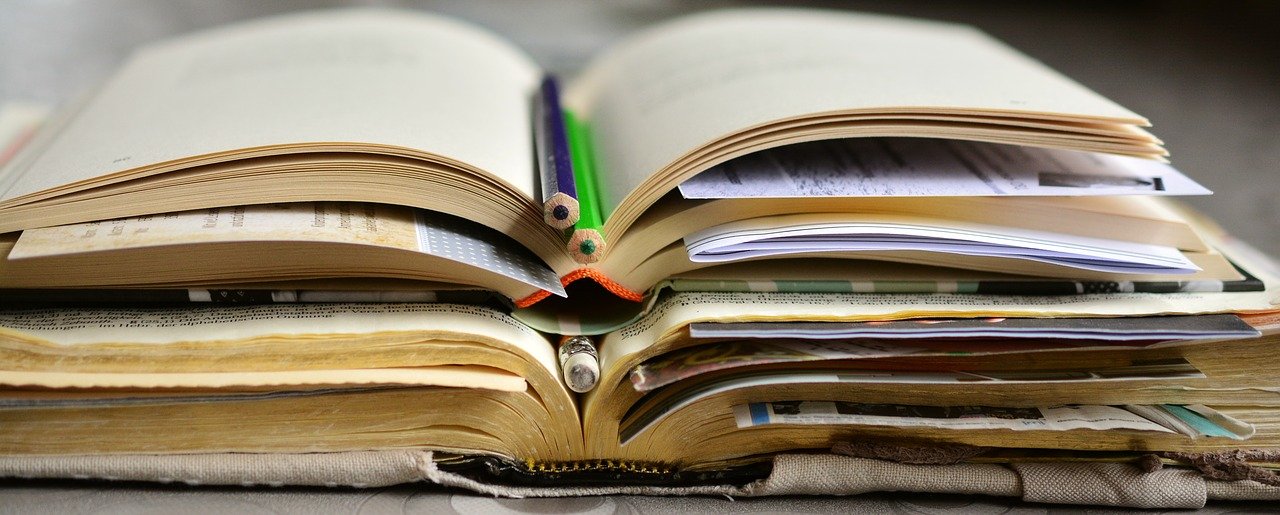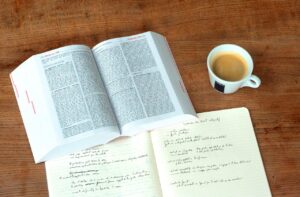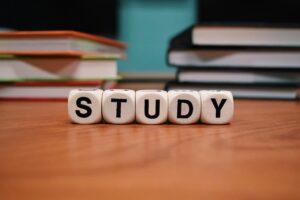税理士試験の受験生の多くは専門校に通いながら勉強を進めているかと思います。
税理士講座のカリキュラムは各専門校によっても異なると思いますが、カリキュラム内で過去問題に触れる時間は少ないのではないでしょうか。
私は通信講座がメインだったのですが、カリキュラム内では過去問題を解くというような時間はありませんでした。
自分で過去問題を解く時間を確保しなければ、解く機会はなかったかなと。
だったら解かなくても良いと思われるかもしれませんが、個人的には過去問題は解いたほうが良いと思っています。
過去問題を解く意味
私自身専門校のカリキュラムを通年受講していましたが、ちらほらテキストや問題集に個別問題として載ってあるのをみて、ほんの一部分を解く程度だったように思います。
それこそ答練(答案練習)のように時間を測って、本試験形式で最初から最後まで通して過去問題を解く時間はなかったなと。
カリキュラムのみにしたがって進めていくとなると、必然的に過去問題をしっかり解く機会が無いということになってしまいます。
もちろん各専門校が作成している答練の問題内に過去問題の改題として作成しているものあったりしますので、それをしっかり解いていれば過去の対策もできていることにはなると思います。
でも答練は答練。過去問題とはまた違います。
私個人的には答練と過去問題は、問題の読み取りやすさが大きく異なると感じています。
私が最初から通して過去問題を解いてみた第一印象としては、
「なんかいつも通りの力が出せないな…」
「いつもの答練のように点が獲れないな…」
そんなことを感じていました。
専門校が作成されている答練は『問題がとても綺麗』な印象です。
表現が適切でないかもしれませんが綺麗というのは問題文としてはもちろんのこと、本当に作り込まれているので不備も少ないですし言い回しもわかりやすく、誤解が生まれないように整えられている印象です。
カリキュラム内でのみの学習だとその答練が中心になるので、その綺麗な問題以外見たことがない、その形に慣れきってしまいます。
では実際の本試験問題はどうかというと、少なからずいつも自分が通っている専門校が作ったものでは無いので問題の雰囲気が異なります。
これだけでも結構な違いを感じられるはずです。
本試験の過去問題に限らず、違う専門校の問題を解いてみても感じることだと思います。
同じ解答なはずなのに、問題文の言い回しだったり表現で解答が全く思い付かないということも十分あります。
他の専門校が作った問題を解くまでは時間的に難しいかもしれませんが、自分がいずれ乗り越えなければいけない本試験の過去ぐらいは知っておかないといけないと思います。
本試験でいつも通りの力を出すためにも、本試験独特の問題文を体感しておく。
いつもの答練と違う雰囲気を味わっておくのも大事なところかと思っています。
過去に出題された問題はしっかり対策しておく
過去の本試験に出題された問題に対して
- 二度も同じ問題は出ないだろうから対策してなくても大丈夫
- もしまた万が一出た時に備えて対策をしておこう
どちらの考え方を取るか。
合格の可能性を少しでも高めたいのであれば後者でありたいものです。
確かに全く同じ問題が出題されるのは考えにくいところ。
けれども似たような問題は出題される可能性は十分にあります。
それに本試験で出題されるレベルを把握するというのも大事なこと。
周りの受験生も過去の本試験で出題された部分はできる状態で挑んでくるでしょう。
そこでもし、同じような問題が出題されて自分が対策していなければ、痛手になってしまいます。
専門校の答練を解いていれば十分だという意見もわかりますが、個人的には過去問題も解いておくべきかと思っています。
カリキュラムも進めながらの過去問題となるので解く時間を確保するのは大変になると思いますが、学習計画を上手く調整しながらこなしていきたいところです。
過去問題を解くタイミングはいつがベストか
実際に過去問題を解くのはいつぐらいからが良いのか。
私の個人的な見解ですが、直前期に入ったぐらいが良いのではないかと思っています。
時期でいうと5月入ったぐらいからでしょうか。
それよりも前となると、特に初学の場合はまだ基礎も固まっていない状態だと思うので、まず基礎学力を固めるのが先決です。
ちなみに私に関してでいうと毎年6月に全国模試があったのですが、その前に1回転(過去5年分)と本試験の約2週間前に1回転するように学習スケジュールを組んでいました。
カリキュラム上で使う教材ではなかったので、直前期に入ったぐらいに書店で買いに行っていました。
私自身がTACだったこともあり解説は見慣れた方が良いと思ったので、同じTAC出版の過去問題集を使っていました。
2024年度版 相続税法 過去問題集直前期はカリキュラム内での答練も頻繁にありましたので、結構大変だった記憶があります。
5科目経験してきましたが、過去問題を解かずに乗り切った科目は1科目もありません。
解く時は必ず本試験を想定する
本試験では難問・奇問が度々出題されます。
そのような問題も含めて、制限時間内に全ての問題に立ち向って正答させるのは至難の業となります。
そうなると、着手するべきところと後にするところの選別が重要になってきます。
いわゆる問題の取捨選択です。
取捨選択の対策という意味でも、過去問題は有効に使えると思っています。
あと、過去問題を解く時は本試験を想定して、時間は測った方が良いです。
そうすることで時間に追われる焦りの中で、本試験独特の問題を体感できて取捨選択の練習もできます。
「ここは得点すべき論点だ」とか「後回しにする論点だ」とか、いつもの答練の時とはまた違った感覚で新たな気付きも出てきます。
その気付きを今後の残りの期間での答練で実践と修正を繰り返して、本試験での立ち回り方を確立させておくと本番でも冷静に焦らず問題に立ち向かえると思います。
それをやらずして、本試験の本番で急に出来ることなんてありません。
本番で実力を最大限発揮するためには、日々の学習でどこまで想定して対策するかに尽きます。
過去問題を解くことまで考えてなかった方は、自身の学習計画に組み込んで上手く活用してみてはいかがでしょうか。
それでは、また次回。